高配当株の勉強をはじめると、書籍の著者や、SNSの発信者によって株を購入するタイミングに違いがあることが分かってきます。
まず私なりの結論ですが、「各銘柄を自分なりに分析して、自分が納得できる安い株価を決めておき、そのタイミングがきた時に買う」これが個人的には最適解かなと考えています。※具体的な各銘柄の購入タイミング(基準数値)については、また後日別記事にて詳しく投稿できればと考えております。
というのも、実際に自分のお金を使って株を買うと、その銘柄毎に自分が購入した株価に対して、株価が上がった、下がったという変化が毎日起き、投資初心者のうちは否が応でも変化後の株価で今自分は得してるのか、損してるのかが気になります。
私も気になってちょこちょこ見ています。
※今の私の場合は、不安で見てしまうという意味ではなく、今後の分析(自身の今の買い時ラインが妥当か否か、修正が必要かどうかの判断の為)の意味合いで気になるという方が正確ですが。
どんなに少ない金額の投資とはいえ、自分が買った時の株価(価値)よりも今時点の株価(評価)は低い(-〇〇%)ですよと表示されると、買い時を間違えてしまった様な気持ちに陥りテンションが下がります。
この記事を書いている現時点で私の各銘柄合算評価は、+評価(+〇〇%)となっているので、高配当株投資そのものへの興味関心もさらに高まり、自然と高配当株投資に関する勉強時間が増える様になりました。
これが逆だと、心中穏やかではなく、高配当株投資の勉強、実践ともに嫌気がさしてきていたのではないかと推測されます。
書籍によっては、購入タイミングを考えず、”ドルコスト平均法”を使って、毎月決まった金額を積み重ねる手法を日本の高配当株でも推奨されているものもあります。
今後の業績が長期的に右肩上がりとなる銘柄であるならば、株価は右肩上がりで上昇する為、結果どのタイミングで購入しようが損にはならないという考え方です。
概ね正しいのではないかと思います。
ただ本質的に思い出したいのは、高配当株投資は”配当金をより多くもらうこと”が「本来の目的」であることです。
「弊社の株を持っていれば、”1株に対して”年間で〇〇円でお渡しします。」という「1株あたり配当金」が企業毎に毎年定められています。
つまりその1株を”高く”買ってしまった人も、”安く”買えた人も、貰える「配当金」は同じということになります。
だったら、安く買えた方がお得です。
また優良な企業の株は、1株だけでなくその後もどんどん株数を増やしていきます。
安い株価のタイミングで購入する方がより多くの”株数”を購入でき、それだけ多くの”配当金”も貰えることに繋がります。
高配当株投資をするにあたっては、約50~80社ほどの企業の銘柄を保有することが推奨されています。
そうなると、事前に100社近くの企業を細かく分析し、自分なりの購入株価ラインや、利回りなどの各種指数に基準を設けておく必要が出てきます。
投資初心者の我々にとっては本当に骨の折れる作業となりますが必要な工程となります。
まとめ
◆購入は、各企業毎に、自身で定めた割安のタイミングで行う。
高配当株投資においても含み益(最低でも±0円)は維持する必要はあります。含み損がある状態での運用だと、せっかくの配当金が意味をなさなくなります。過度にキャピタルゲインを狙う必要は無い投資手法ではありますが、少しでも多く配当金の恩恵を受け取れるように、自身が購入する企業に関しては、購入タイミングの基準(株価や指標)を事前に調べて決めておきましょう。
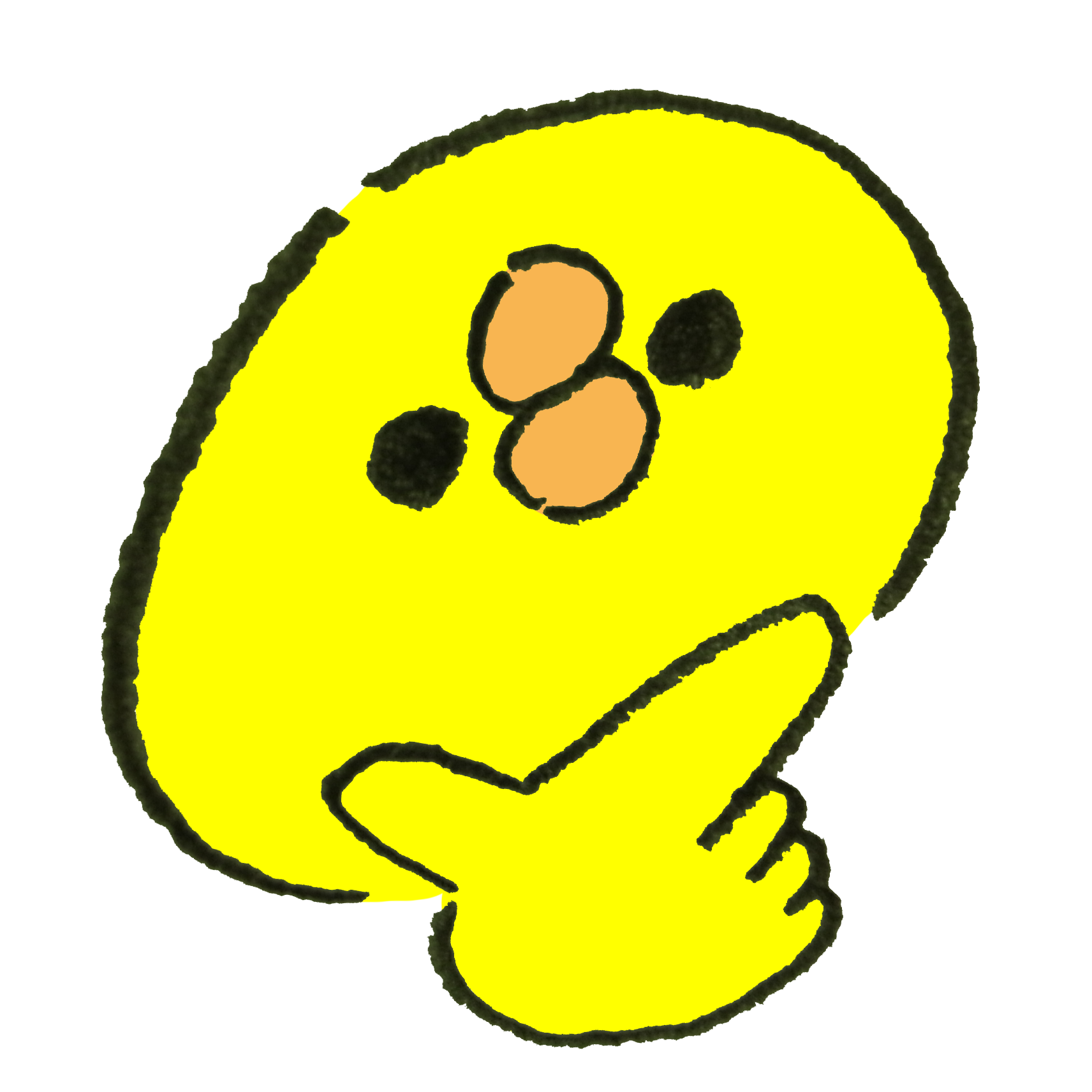
コメント